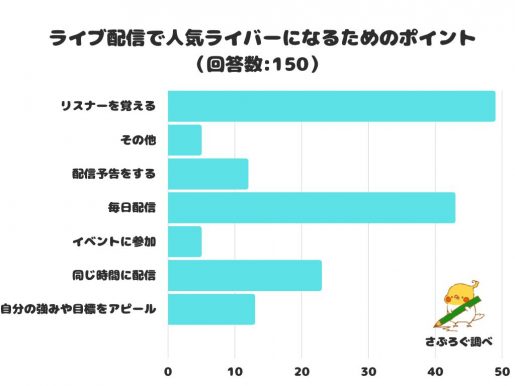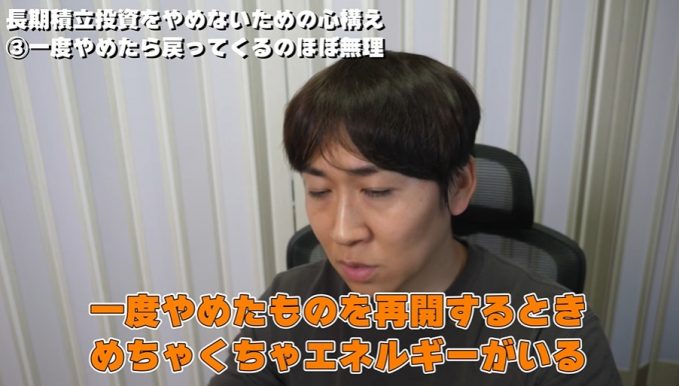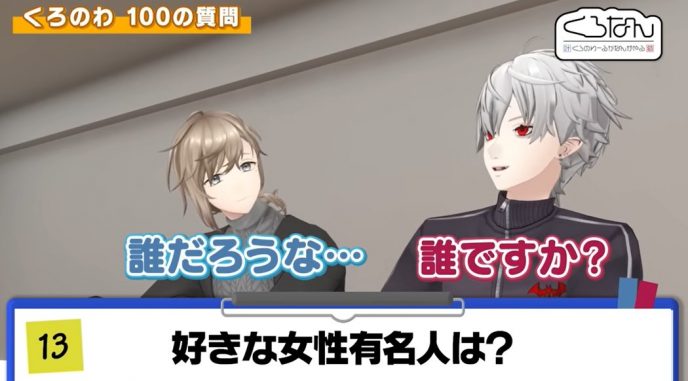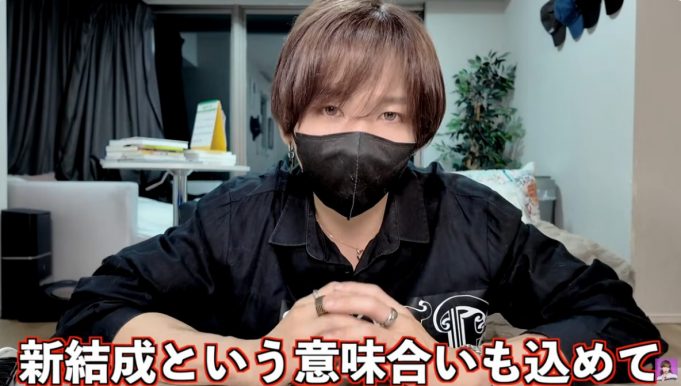『素潜り漁師マサル』の「冬の山が過酷すぎてガチで死にかけました。」は、1ヶ月のサバイバルに挑む過酷な記録。
人間は14日間何も食べなくても生きられるが、今回の挑戦は30日。初日から火を起こせず、最低気温5度の中で徹夜を強いられたマサル。
夜の山に響く鹿の鳴き声、止まらない頭痛と吐き気、そして体の芯まで冷えていく感覚。朝を待つことがこれほど切実な願いになるとは、誰が想像できただろう。
当たり前が奪われた時、人は初めて気づく
火がつかない。それだけで全てが狂い始める。
湿気が異常に高く、日が当たる時間はわずか4時間。日陰になった瞬間、すべてが湿り始める。
500メートル歩いてやっと見つけた乾いた木。
「乾いてるだけでこんなに感動できるなんて」というマサルの言葉が、日常の有り難さを痛いほど教えてくれる。
やっと火を起こせた時の喜びは、まるで命を取り戻したかのよう。
食事も入浴も暖房も、私たちが何気なく享受している全てが、実は生死を分ける境界線の上にある。
命をいただく覚悟。渋柿と箱罠が映す生きることの重み
唯一見つけた柿は渋くて食べられない。箱罠を仕掛け、動物の捕獲を試みるマサル。
「動物って全部可愛い顔してる」と語りながらも、食べるために命を奪う覚悟を決める姿に、生きることの本質が浮かび上がる。
私たちは普段、パックに入った肉を買い、その裏にある命と向き合うことはない。
だが、生きるとは誰かの命をいただくこと。
マサルの葛藤は、現代人が忘れかけている根源的な問いを突きつける。
極寒の山で彼が手に入れたのは、火という温もりと、生きることへの畏れだったのかもしれない。